(2024年3月18日更新) [ 日本語 | English ]
有珠山 / サロベツ泥炭採掘跡
1986年, 2006年の有珠山火口原. ワタスゲ・エゾカンゾウ
雑録 [ 報告書 | 植物学会 | 生態学会 | 講演(含 他学会要旨) | 書評・コラム | 報告書 ( 温室 )| 文献 ]
|
温室には、毎年といって良いほど、お世話になってるが、改組の度に、微妙に報告書の名前かが変わって来てる。使っている立場では、、何が変わったかと聞かれると名前だけ、と答えそう。ここには、ファイルが残ってたものを載せておこう。
[
|
|
|
地球環境科学院 統合環境科学部門 自然環境保全分野
露崎史朗・Lea Végh・張信燕・周灵灵
|
埋土種子を含めた種子集団の発芽タイミングは、その後の実生の消長を決める重要な要因である。そこで、温室において埋土種子を含めた植物の種子発芽・実生成長に関する3種の実験を行った(実験3は継続中)。全実験で発芽生育床にはプラスチックトレイ中にバーミキュライトを敷設した後、その上に各土壌を敷き詰め作成した。 (1) 土壌水分・土質と種子発芽・実生成長との関係 同一降水条件下においても土質が異なれば発芽・成長が異なる。特に、地表面は、火山においては軽石や火山砂に覆われ、一方、高層湿原ではミズゴケ泥炭に覆われている。そこで、これらの土質の違いが種子発芽・実生成長に与える影響を温室にて調べた。エゾノギシギシおよびヒキオコシの種子を2017年10月に北大構内から採取した。土壌は、軽石・川砂・泥炭の3種類である。種子を低温湿層処理後に、50粒ずつをトレイに播種した。スプリンクラー自動散水回数を2パターン設け、降水頻度勾配を作った。よって、実験デザインは(2種 × 3土質 × 2降水 × 5反復)で計60トレイを使用した。発芽観察は、発芽が10日以上認められなくなるまで毎日行い、エゾノギシギシでは実験開始から一ヶ月後に終了した(ヒキオコシは粃が多く発芽は殆どなかった)。発芽実験終了後に、実生を回収し60°Cで48時間乾燥後に、重量、シュート長、根長、葉長を測定した。エゾノギシギシでは、低降水区で発芽数が若干高いことを除けば降水処理間で顕著な差は認められなかったが、土質は発芽速度に大きく影響していた。バイオマスは、処理間で顕著な差は認められなかったが、葉長は川砂処理区で根は軽石処理区で長くなる傾向があった。したがって、発芽・成長に対する降水と土質との相互作用は弱いことが示唆された。 |
(2) ヨシ湿原における埋土種子集団発達機構 サロベツ泥炭採掘跡地では、高層湿原への復元が試みられているがヨシの侵入が著しく他種の定着が抑制されている地域がある。この要因の一つに埋土種子集団の発達抑制が考えられる。そこで、温室にて発芽実験により埋土種子集団構造を測定した。埋土種子集団は季節性があるため、種子発芽後の夏季(2017年)と種子散布直後の秋季(2016年)に、それぞれ81個の土壌サンプル(表面積20 cm2, 深さ5 cm)を採取し、温室にて発芽実験を行った。夏季サンプルからは、419個体の発芽が認められ、優占種は、ヌマガヤ、ミカヅキグサ、エゾリンドウ、ホロムイスゲ、コガネギクおよびヨシであったが、ヨシ湿原においてはヌマガヤとエゾリンドウの発芽数は少なかった。ヌマガヤはミズゴケ定着の鍵種であるが、ヨシによる埋土種子集団の発達抑制がミズゴケ定着が遅延する一因となることが示唆された。
サロベツ泥炭採掘跡地では、高層湿原への復元が試みられているがヨシの侵入が著しく他種の定着が抑制されている地域がある。この要因の一つに埋土種子集団の発達抑制が考えられる。そこで、温室にて発芽実験により埋土種子集団構造を測定した。埋土種子集団は季節性があるため、種子発芽後の夏季(2017年)と種子散布直後の秋季(2016年)に、それぞれ81個の土壌サンプル(表面積20 cm2, 深さ5 cm)を採取し、温室にて発芽実験を行った。夏季サンプルからは、419個体の発芽が認められ、優占種は、ヌマガヤ、ミカヅキグサ、エゾリンドウ、ホロムイスゲ、コガネギクおよびヨシであったが、ヨシ湿原においてはヌマガヤとエゾリンドウの発芽数は少なかった。ヌマガヤはミズゴケ定着の鍵種であるが、ヨシによる埋土種子集団の発達抑制がミズゴケ定着が遅延する一因となることが示唆された。(3) 発芽実験による有珠山埋土種子集団構造の測定 (継続中) 大規模撹乱後の植生回復には、埋土種子バンクが関与していることが多い。そこで、埋土種子組成の時空間的変化を調べるため、有珠山の様々な植生から採取した土壌を用いて発芽実験を2016年から温室において行っている。土壌は、表層から深さ0-5 cmおよび15-20 cmの部分を採取した。2016年度秋に採取した土壌の発芽実験は、2016年12月から2017年5月まで実施した。2017年秋に採取した土壌に対する実験を2018年1月18日から開始し、継続中である。概要としては、優占種は、タチツボスミレ、ミズ、スゲ類であった。現在継続中の実験を最後とする予定であり、本実験終了後、速やかに解析を行い成果を報告する。 |
地球環境科学院 統合環境科学部門 自然環境保全分野
露崎史朗・周灵灵・Mukhlish Jamal Musa Holle・Lea Végh・賈雨萌・張暁理
|
生態系発達過程を知る上で、種子発芽・実生成長の特性を知ることは重要である。多くの種子は埋土種子として土中に蓄積し、生態系の発達に影響することがある。そこで、温室において埋土種子を含めた植物の種子発芽・実生成長に関する種々の実験を行った。全実験で発芽生育床にはバーミキュライトを敷設したプラスチックトレイを用いた。 (1) 種子発芽・実生成長実験 (a) リターサイズが種子発芽・実生成長に与える影響: リター堆積は、その分解度合いに応じ、発芽に対して水分保持による発芽促進などの正の影響と根成長阻害などの負の影響を与える。そこで、イヌタデおよびエゾノギシギシの種子を対象に、リターサイズを変えたトレイを準備し、種子発芽および実生成長に与える影響を温室において実験した。その結果、イヌタデの種子発芽は粗いリター上で大きく低下した。一方、エゾノギシギシの成長は、細かいリター上で良好であった。したがって、リターは分解が進むにつれて総体的に負の影響から正の影響に転ずる可能性が示唆された。 (b) 火災強度に応じたイヌタデ種子発芽特性: イヌタデ種子は、煙誘導発芽であることが知られているが、火災強度の対応関係は不明の点が多い。そこで、激害を想定した木灰と微害を想定した木炭をバーミキュライト上に広げたトレイとこれらを、その上で発芽実験を行った。その結果、発芽は木炭上で最も高く、一方、木灰上では最も低かった。これらのことは、火災強度に応じて火災後のイヌタデの発芽様式は大きく異なることを示している。 (c) ミネヤナギパッチによる種子発芽・実生定着への定着促進効果: 北海道渡島駒ヶ岳では、ミネヤナギが低木パッチを形成し微環境を改善することで他種の侵入が促進される定着促進効果が認められている。個々の微環境改変が種子発芽と実生成長に与える影響について、温室において微環境(温度・土壌湿度・リター堆積・光)を操作し検証した。その結果、温度はあまり重要ではなく、光・リター堆積が種子発芽と実生成長に影響していることが明らかとなった。また、埋土種子実験からミネヤナギパッチには種子トラップ効果があることが確認された。 |
 (2) 埋土種子発芽実験 (継続中)
(2) 埋土種子発芽実験 (継続中)(a) ヨシ植生と埋土種子集団の関係: サロベツ泥炭採掘跡地においては、高層湿原への生態系復元が試みられているが、場所によってはヨシの侵入が著しく他種の定着が抑制されている。ヨシを減少させることで、埋土種子からの多種の再生が期待されるが、埋土種子集団の発達度合いは未詳である。そこで、ヨシ植生とそれに近接するヌマガヤ草地から泥炭を種子散布完了後の2016年晩秋に採取し、それらを用いて埋土種子発芽実験を行っている。現在も発芽中であるが、少なくともヨシは埋土種子を発達させないがヌマガヤの埋土種子の発芽は顕著に認められている。今後、発芽が完了するまで実験を継続し、結果を整理する。 (b) 有珠山埋土種子集団構造の測定 (継続中): 植生回復には、土壌中に埋土した種子バンクが関与していることが多い。そこで、埋土種子組成の時空間的変化を調べるため、昨年と同様(昨年度成果報告参照)の発芽実験を温室にて行った。また、本年は、表層から深さ5 mまでの土壌に加えて深さ15-20 cmの土壌も採取し、埋土種子集団を比較した。現在、2月末現在で131個体が発芽している。昨年の実験は4月下旬に実験が完了しており、今後も発芽数は増すと予測され、それらの結果を合わせデータの整理と解析を行う。 |
地球環境科学院 統合環境科学部門 自然環境保全分野
露崎史朗・趙新雪・周灵灵・張倩倩・Mukhlish Jamal Musa Holle・Lea Vegh
 各種の種子発芽・成長特性を明らかにすることは、生態系発達過程を知る上で重要である。そこで、温室において植物の発芽成長に関する3実験を行った。全実験で発芽生育床には縦20 cm × 横15 cm × 深さ5 cmのプラスチックトレイを用いた。
各種の種子発芽・成長特性を明らかにすることは、生態系発達過程を知る上で重要である。そこで、温室において植物の発芽成長に関する3実験を行った。全実験で発芽生育床には縦20 cm × 横15 cm × 深さ5 cmのプラスチックトレイを用いた。(1) 種子発芽・成長実験 アキノキリンソウ(Solidago virgaurea)は、湿原から荒地までの様々な生息地に定着している。湿原において本種が定着できる要因を知るために、10月下旬に道北で採取した本種種子に対して、土壌(基質)・肥料濃度を操作した種子発芽および実生生育実験を行った。発芽完了から1ヶ月後にNDVI(植生指数)を測定し、生存実生を刈り取り地上部と地下部に分けバイオマスを測定した。土壌はミズゴケとピートモスの2種類、肥料濃度は0, 0.09, 0.45 g/100 cc/週の3種類とした。30トレイに、それぞれ50種子を播種し、スプリンクラー散水を日に7回(30秒)行った。一回の散水量は、平均0.032 ml/cm²である。発芽数は発芽完了まで毎日記録した。発芽パターンは、基質には影響されなかった。バイオマスおよびアロケーションは、基質よりもむしろ施肥量により変動していた。地上部バイオマスは地下部バイオマスより高い値を示した。アキノキリンソウに近縁であるが帰化植物であるオオアワダチソウ(S. gigantea)について、散水量を変えた以外は上記と同様の実験を行った。オオアワダチソウは、アキノキリンソウに比べ乾燥した土壌において発芽・成長が良好であることが示された。 |
アレヂマツヨイグサ(Oenothera biennis)の発芽特性に対するリター量の影響を把握するために、リター量を変化させた実験を行った。種子およびリターは2015年11月に北大構内から採取した。リターにはシラカンバ葉を用いた。本種の種子発芽は、低温処理が必要なため恒温器内温度を2oCに設定し3週間にかけて湿層処理を行ったものと行わなかったものを発芽実験に供した。リターは、0, 1.5, 3, 6 g/トレイに設定し50種子播種を5反復準備し温室で実験を行った。播種以降、毎日発芽数を測定した。リターのないトレイで、発芽開始は非湿層処理種子で早かったが発芽率は12.4%と低かった。一方、湿層処理種子では発芽率は65.6%に達した。全てのリター処理区では、発芽率は8%以下であった。これらのことから、オオアワダチソウは僅かなリター蓄積でも種子発芽が大きく阻害されることが明らかとなった。 (2) 埋土種子発芽実験 (継続中) 植生回復には、土壌中に埋土した種子バンクが関与している。そこで、有珠山において1910年噴火後に発達した複数の植生から100 ccの土壌を合計70箇所から採取し、発芽実験を行っている。これまでに、127実生が発生し、未同定実生については別テーブルに移し生育させている。 (3) 栄養繁殖実験 (継続中) 道内の火山地域に優占するミネヤナギ(Salix reinii)パッチは、他種の侵入定着に大きく影響している。そこで、ミネヤナギ枝条をトレイ中で発根成育させ枝条密度(5, 7, 9枝/トレイ, 5反復)が種子発芽と実生成長に与える影響を検出する目的で実験を行っている。本年秋に渡島駒ヶ岳で優占種種子を採取し、それらを実験パッチ中に播種し発芽・成長を測定する予定である。そのため、予備段階としてミネヤナギの良好な発根条件を知るために温室にて発根実験を試みた。2015年秋に駒ヶ岳にてミネヤナギ枝条を採取し、これらに発根促進剤に浸漬し発根確認後にトレイに移植した。しかし、多くの枝では、発根が停止し開葉も見られなかった。この要因として、枝条採取時期、土壌栄養、水ストレス等が考えられ、これらの点を改善し実験を行う予定である。 |
地球環境科学院 統合環境科学部門 自然環境保全分野
露崎史朗・宮崎紀子・粟琳・Mukhlish Jamal Musa Holle
|
各種の種子発芽および実生成長の特性を明らかとすることは、生態系の発達を知る上で必要である。そこで、温室において植物の発芽成長に関する3つの実験を行った。いずれの実験も継続中であり予報となるが、得られている知見は以下の通り。なお、全実験で発芽生育床には縦20 cm × 横15 cm × 深さ5 cmのプラスチック容器を用いた。 (1) ヌマガヤの発芽・生育に関する実験 ヌマガヤは湿性遷移初期の代表種である。本種の定着要因に関与する土壌、土壌栄養分および種子密度に関する実験を行った。播種密度(5, 10, 20種子)、施肥濃度(0, 10, 50 ml, 9.0 g Hyponex/l/週)、土壌(ピートモスとミズゴケ)を変え、ヌマガヤの発芽・成長を測定した。10月下旬にサロベツ湿原泥炭採掘跡地で採取したヌマガヤ種子約1000個を1カ月低温処理後に温室にて播種を行った。その結果、発芽率はピートモス、ミズゴケともに46%であった。種子密度については、5個で48%、10個で52%、20個で39%と10個で一番高い値を示した。施肥については、0 mlで40%、10 mlで52%、50 mlで47%となり10 mlで一番高い発芽率を示した。NDVIを播種2カ月後に、非接触NDVI測定装置により、各容器で3回測定し平均をとった。NDVIは、ピートモス上で0.47、ミズゴケ上で0.54であった。ただし、ミズゴケ上にはコケ類が発生していた容器もあった。種子密度については、5個で0.51、10個で0.49、20個で0.52となり、明瞭な違いは見られなかった。施肥については、0 mlで0.40、10 mlで0.53、50 mlで0.59となり、栄養濃度が高い方が高い値を示した。以上のことから、発芽率は土壌の質に依存せず、適度な栄養と密度の時に高くなること、NDVIはミズゴケ上で栄養濃度が高い方が高い値を示し、密度差はないことが分かった。今後、ヌマガヤを刈取り、バイオマスを測定しNDVIとバイオマスの相関を確認する予定である。 |
 (2) イヌタデの発芽・成育特性に関する実験
(2) イヌタデの発芽・成育特性に関する実験イヌタデは、一年生草本であり数か月で開花結実に至る。成長が遅いヌマガヤにおいて測定が困難である有性繁殖器官を含めたバイオマス測定とNDVI比較が可能となる。そこで、おおむねヌマガヤに準ずる実験を行った。ただし、土壌としてはピートモスのみを用いた。種子は、10月中旬に北大構内で採取し、1か月の低温処理を行った後に温室にて播種した。ヌマガヤと異なり、施肥量が増すほど成長は良くなった。その結果、施肥量の増加に伴いNDVIは高くなった。あわせて、SPAD値(クロロフィル量に関連した値)を測定したが、SPAD値とNDVIには、概ね正の相関が認められた。今後、これらの植物体を刈取り行い、バイオマス測定を行う予定である。 (3) オオイタドリ・ススキ実生の競合実験 渡島駒ヶ岳を始めとする日本の火山では、オオイタドリ・ススキの分布が認められる。これら2種はともに、遷移初期に優占する多年生草本であるが、野外ではオオイタドリパッチ中にはススキの侵入は見られるが逆は見られない。この要因を明らかとするために10月に駒ヶ岳で採取したこれら2種の種子を恒温器中で種々の条件下で発芽させた実生を用いた単播および混播実験を行っている。 |
地球環境科学院 統合環境科学部門 地球温暖化評価分野
露崎史朗・アピア カトリン
|
アフリカでは、人為による森林火災が増加しつつある。特にガーナにおいては鉱山採掘跡地等で発生した森林火災撹乱後の生態系復元は重要な課題となっている。これまで、温室においてアフリカ(ガーナ)の森林火災後に播種されることが多いVigna unguiculataとColocynthis citrullusの種子を用いて、火災に伴い発生する木灰と土壌水分が発芽に与える影響を調べてきた。その結果、V. unguiculataは厚さ0.5 cmの木灰下ですら発芽できず、火災後に木灰が蓄積すると再生は期待できないことが明らかとなった。一方、C. citrullusは、発芽に時間を要するが、厚さ数cmの木灰下でも土壌水分が十分高ければ発芽できることが分かった。 |
しかし、森林火災は、木灰蓄積などによる土壌条件変化を介した発芽への影響などの他に、大量の煙を放出することで発芽に影響することが知られている。特に、南アフリカのフィンボスから、煙誘導発芽と言われる、煙中の成分が種子の発芽を誘導し、火災後に速やかに植物群集を回復させる種が数多く存在することが報告された。そこで、木灰下では発芽できない植物種の中に、木灰下でも煙刺激を受ければ発芽する種子が存在する可能性を検討するため、煙誘導発芽を模した実験を温室にて行う計画を立て2013年度中に実験を実施する予定で利用申請を行った。残念なことに、実験の主担当予定者の事情により実施を断念したが、機会が得られれば改めて、本温室を利用し本実験を行わせて頂きたい。 |
地球環境科学院 統合環境科学部門 地球温暖化評価分野
露崎史朗・Kwon TaeOh・北條 愛
|
【目的と方法】 火山噴火や津波による撹乱直後の高ストレス環境下において、遷移速度を決める機構の一つとして正の種間相互作用が着目されている。ファシリテーション(定着促進効果)は、ある種の存在により他種の定着が促進される正の種間相互作用を意味し、安定群集における種間競争とは対照的な種間関係である。ファシリテーションに関する種々の実験は、これまで数年間にわたり温室で継続して行っている。特に、ミネヤナギ、カラマツは菌根(主に外生菌根)形成種であり、菌根を通した間接的定着促進効果を明らかとする必要があるため、窒素欠乏状態となる火山地域での菌根連結(common mycorrhizal network)を介した定着促進作用に焦点を置いた研究を行っている。そのため、環境と水分・栄養分移動を制御した条件下で植物成長に関する実験を進めている。本年度は、これらに加えて、津波等に等に伴う土壌塩分ストレスの増加が海岸林の再生に与える影響を定量化するために、北海道の海岸林の代表種であるカシワを材料にポット試験を行った。主な実験方法は、以下の通り。 (1) 渡島駒ヶ岳における優占種であるミネヤナギ(Salix reinii)が他種に与える影響を定量化するために、温室において、ミネヤナギパッチを移植したポットを用意し、そのポットと非移植ポット(コントロール)中にカラマツ(Larix kaempferi)種子を播種し、定期的に発芽および成長を調べた。用土には、駒ヶ岳で採取した火山灰およびバーミキュライトを用いた。 (2) 地下部におけるミネヤナギとカラマツ間の菌根菌を介した相互作用を検出するために、温室においてポット実験を行った。ミネヤナギとカラマツの間の根圏部に4種類のフィルターにより遮蔽処理(接触なし・栄養分のみ移動・菌根菌も移動・全て移動)を施し栄養分移送を制御し成長を測定した。 (3) カシワの2-3年生稚樹を材料に、温室内で塩分濃度を変えた灌水を行うことで、塩分勾配を形成し、それらに対するカシワの応答を成長・形態・光合成特性の面から比較した。 |
 【結果と考察】
【結果と考察】カラマツ発芽率は、いずれの実験区でも60%以上であり、ミネヤナギがカラマツの発芽に対する影響は弱く、ミネヤナギはカラマツの発芽にはほとんど影響していない。ミネヤナギにより、噴火降灰物の栄養状態は改善され、カラマツ実生の地上部-地下部バイオオマス比(T/R比)は増加していたが、その一方でミネヤナギによる被陰は実生成長量を低下させていたがT/R比に変化はなかった。したがって、ファシリテーションの主な要因は地下部に起因するものと考えられる。そこで、根圏における遮蔽実験を行い、物質移動に対する根系の寄与を見積もった。 カラマツの成長にとって、火山灰中の栄養分は、ミネヤナギパッチ内の方が、カラマツのみが生育しているところよりも適していた。地下部における物質移動を制御した遮蔽実験からは、窒素(NO3-, NH4+)の移動はミネヤナギの存在により促進されており、それらの移動に伴い火山灰中のpH、ECも変化しえいることが明らかとなった。これらのとこは、菌根を介したファシリテーションの存在を示唆しており、野外実験の結果と合わせ解析を進めている。 カシワ稚樹に対する塩分操作実験では、当初の要因計画実験からデザインに変更があったことと、それに伴う様々なアーティファクトが生じたため、データ解釈に困難が生じている。今後、必要に応じ、再実験あるいは新たな要因計画実験を行うことにより曖昧となった点を明らかとしたい。 |
地球環境科学院 統合環境科学部門 温暖化影響評価分野
露崎史朗・Kwon TaeOh・Appiah Catherine
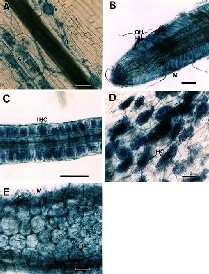 【目的と方法】
【目的と方法】ファシリテーション(定着促進効果)は、ある種の存在により他種の定着が促進される現象のことで、火山噴火や森林火災といった撹乱直後の遷移速度を決める上で重要な機構であるが、不明の点が多い。そこで、本実験では、種子発芽段階におけるファシリテーションに焦点を当て、以下の実験を行った。撹乱後の侵入種間相互作用を定量化するために、有珠山で優占するオオイタドリ(Polygonum sachalinense)の種子発芽に対するヒメスゲ(Carex oxyandra)の影響と、駒ケ岳で優占するカラマツ(Larix kaempferi)の種子発芽と実生成長に対するミネヤナギ(Salix reinii)の影響を、温室にて実験し評価した。また、アフリカ(特にガーナ)における金採掘跡地に発生した森林火災撹乱後の生態系復元手法を探るために、火災後に播種されることが多いササゲ(Vigna unguiculata, Black-eyed pea)とスイカ(Colocynthis citrullus, Egusi)の種子発芽に対する火災に伴い発生する木灰と土壌水分が与える影響を、実験計画法による方形実験デザインを用いた温室実験により評価した。即ち、スプリンクラーの散布回数を調整することで、土壌水分勾配を作り、かつ、木灰の厚さを0.0(木灰なし), 0.5 1.0 cmに調整し、木灰下に種子を播種し発芽実験を行った。 |
【結果と考察】 オオイタドリの発芽率は、有珠山火山灰上では25%であったが、ヒメスゲ下ではほぼ0%となった。そこで、ヒメスゲ地下組織から分泌される化学物質中にオオイタドリの発芽抑制物質が存在する可能性を確認する実験を進める予定である。また、ヒメスゲ-オオイタドリ種間関係が遷移過程に果たす役割を明らかとするために、発芽したオオイタドリとヒメスゲ間に対し、土壌栄養と水分の共有関係(hydraulic lift)を中心に温室実験を進める。カラマツの発芽率は、駒ケ岳火山灰上で約75%、ミネヤナギと共存時には65%となり、ミネヤナギがカラマツの発芽に対する影響は弱い。したがって、野外で観察されているミネヤナギのカラマツに対するファシリテーションは発芽率によるものではない。そのため、温室にて実生成長と土壌栄養の関係を追跡調査し、あわせて植物の化学成分分析を進める予定である。ミネヤナギ、カラマツは菌根(特に外生菌根)を発達させる種であり、菌根を通した栄養分移動とそれに伴う促進効果を明らかとする必要がある。さらに、窒素・リン欠乏状態にある火山地域での菌根連結(common mycorrhizal network)を介した種間定着促進関係性に焦点を置いた研究を行う。そのため、温室で、環境と水分・栄養分移動を制御した条件下で、植物成長に関する実験を進める。これらは、必要に応じ、追加実験を行う。 ササゲは、0.5 cm以上の厚さとなる木灰下では全く発芽せず、木灰がないときにのみ発芽が見られ、火災後に木灰が蓄積したところでの発芽は困難であることが示唆された。スイカは、ササゲに比べて発芽に時間を要したが、いずれの木灰の深さでも土壌水分が十分高ければ発芽した。現在、刈り取った実生のバイオマスについて実験区間の差を検討している。今後、実験に用いる種数を増やし、より火災後の復元に適切な種の選択を行う予定である。 |
地球環境科学院 統合環境科学部門 温暖化影響評価分野
露崎史朗・保要有里・平田亜弓
|
種子発芽および実生生存・成長の成功は、環境に大きく支配される。そのため、植物の繁殖成功と環境変化との対応関係を明らかとするためには、環境を適切に操作できる室内実験を行い、その結果と野外実験結果との比較が必要となる。そこで、温度調節や潅水が調節可能である創成科学共同研究機構実験生物施設植物ガラス室において、室内実験を行った。さらに、野外実験に用いる実験材料の調整を温室にて行った。 【目的と方法】 絶滅危惧種であるナガバノモウセンゴケ(ナガバ)および近縁種のモウセンゴケの実生の生存・成長特性を比較することで、ナガバが絶滅危惧種となる要因を明らかとすることを目的として、温室と野外において実験を行った。特に、これら2種の生育する湿原環境をシュミレーションするために、2008年秋にサロベツ湿原泥炭採掘跡地から採取した種子から発芽させた実生を用いて、水位を固定した実験系を温室内で組み、生存および成長を測定した。水位は、野外における測定結果をもとに、1, 3, 5, 9 cmに設置した。土壌基質としては、サロベツ泥炭および園芸用ピートモスの2種類を用いた。実生の生存を2カ月間追跡し、追跡の最後に生存個体を刈り取り、成長量の指標として乾燥重量を測定した。 あわせて、湿原における遷移初期侵入種の光応答様式を明らかとするために、野外において移植実験を行う材料としてミカヅキグサおよびヌマガヤ実生の調整を温室で行った。これらの調整実生は、6月中にサロベツ泥炭採掘跡地の中でも植被が低く遷移初期と見なすことのできる地域に移植した。2008年度に温室で行った有珠山および仏沼から採取した土壌での埋土種子発芽実験は、2008年度中におおむね完了したが、若干の未同定種の生育を2009年9月まで行った。なお、その結果は、昨年の報告書中で述べている。 |
【結果と考察】 2種のモウセンゴケの生存率は、サロベツ泥炭上、ピートモス上のいずれにいても5-9 cmという低い水位でより低くなった。さらに、同じ水位であればナガバの生存率はモウセンゴケより高い傾向を示した。移植2ヵ月後の乾燥重量は、どの水位においてもナガバの方が大きかった。この結果は、野外における移植実験の結果とおおむね一致した。ナガバの成長量は、モウセンゴケよりも大きく、さらに、水位が5- 9 cmでより大きな値を示した。したがって、ナガバの実生生存・成長は、高い水位が保たれるならばモウセンゴケよりも良好であるといえた。よって、ナガバは、十分な種子移入や適切な発芽条件が満たされれば、個体群維持は可能であることが示唆された。  温室にて生育させたミカヅキグサ・ヌマガヤ2種の実生を野外に移植し、これらに様々な光条件を与えることにより、10-20%程度の紫外線量の変化であれば、遷移初期種は、応答様式は異なるが対応可能であり、成長量に影響はないことが示された。これらの結果をもとに、引き続き、各種の発芽・実生生存・成長を温室および野外において比較する予定である。
温室にて生育させたミカヅキグサ・ヌマガヤ2種の実生を野外に移植し、これらに様々な光条件を与えることにより、10-20%程度の紫外線量の変化であれば、遷移初期種は、応答様式は異なるが対応可能であり、成長量に影響はないことが示された。これらの結果をもとに、引き続き、各種の発芽・実生生存・成長を温室および野外において比較する予定である。
|
地球環境科学院 統合環境科学部門 温暖化影響評価分野
露崎史朗・木村英雄・小山明日香・保要有里・平田亜弓・斎藤達也
|
攪乱後の植物群集回復には、発芽せずに土壌中に埋もれていた種子、いわゆる埋土種子が大きく寄与することがある。埋土種子集団形成状態測定法の一つに発芽実験法があり、幅広く用いられるが、適切な温度調節や潅水が必要となる。また、野外実験において植物個体サイズの調整は、移植に際し成育サイズ等のバラつきを減らすため重要である。そこで、本条件を満たせる創成科学共同研究機構実験生物施設植物ガラス室において、発芽実験法により埋土種子集団測定、および実験材料の成育を行った。 【目的と方法】  実験生物施設温室において行った主な実験は以下の3点である。
実験生物施設温室において行った主な実験は以下の3点である。1. 仏沼(青森県三沢市)は、ヨシ優占湿原であり、30年間に渡り春先に火入れが行われている。火入れが埋土種子集団に与える影響を定量化するために、2007年秋(昨年度報告書参照)および2008年夏に、異なる火災強度の地域から100 cm3の土壌サンプルを20ずつ採取し、リターが存在する場合にはリターも採取し、それらの発芽実験を温室にて行い、埋土種子集団構造を測定した。 2. 有珠山火口原では、1977-78年噴火により主に軽石・火山灰からなる噴火降灰物(テフラ)の堆積が、数 m規模で起こった。これまで、噴火10年後および20年後に、テフラの厚さが1 m前後の地域で、埋没した噴火前の土壌(旧表土)を採取し、これらの土壌中に埋もれた種子の生存状況を調べている。本年度は、噴火30年後の埋土種子の生存状況把握を行った。土壌は100 cm3(表面積20 cm²)採土缶を用い300サンプルを採取した。そのうち、半数を温室にて発芽実験に供し、残りは遠心浮上法により土壌からの種子抽出を行った。 |
3. 環境ストレスに対する植物応答を解析するために、10種の種子を、恒温器または温室にて発芽させ、温室で成長させた。これらの材料を、温室にて継続成長、またはサロベツ湿原泥炭採掘跡地に移植し、ストレス(主に紫外線)応答に着目し、成長追跡を行っている(継続中)。 【結果と考察】 1. 仏沼採取サンプルから、2007年秋に39,000種子/m²、2008年夏に31,000種子/m²の発芽が観察された。合計39種が確認され、火災強度の強い地域で種数・種子密度ともに高かった。優占種は1年生草本のアオミズ、越年生草本のタネツケバナ、ノミノフスマ、多年生草本のヒメイ、コウガイゼキショウであった。アオミズ、タネツケバナ、ノミノフスマはリター中に多く、ヒメイ、コウガイゼキショウは土壌中に多く蓄積していた。ヨシの埋土種子は確認されなかった。土壌中に多く見られた種の種子サイズは、リター中で見られた種よりも小さい傾向があった。埋土種子集団の発達は良好であり、火災の影響は負となる可能性が低く、植生回復に埋土種子集団は寄与しうることが示唆された。 2. 噴火30年後において、未だ1,000/m²の種子の生存が確認された。自然状態で30年以上に渡り、高密度で種子が生存することを実証した研究は、始めてである。優占種は、ヒメイ・エゾノギシギシであった。エゾノギシギシは、噴火10年後、20年後の測定でも高密度での生存が確認されており、過湿状態にも関わらず、冷所・無光状態ならば長命種子であことが証明された。 3. 温室において発芽・成育させた材料を、野外移植し、成長追跡を行った。その結果、高さ成長に関し、環境ストレスに対する応答は種間で異なることが明らかとなった。発芽に関しては、オオアワダチソウリターは、クサヨシに抑制効果,オオイタドリに促進効果が確認された。実生生存率は、リター堆積により環境ストレスが軽減された場合には高くなることが示された。現在、本移植個体を採取し、色素定量中である。モウセンゴケ属2種は、温室で成育中であり、雪解け後に、野外に移植する予定である。 |
地球環境科学院 統合環境科学部門 温暖化影響評価分野
露崎史朗・江川知花・木村英雄
|
大規模撹乱を受けた湿原では、土壌中の発芽しない状態でいる種子(シードバンク)が植生遷移の方向を決定することが多い。しかし、シードバンク発達様式は攪乱の種類・規模・頻度・強度等により大きく異なるため不明な点が多い。そのため、本研究室では、攪乱後の湿原における植生遷移機構解明を目的に、シードバンク発達様式の体系化を目指し、北海道大学先端科学技術センターガラス温室において、継続的にシードバンク発芽実験を行ってきた。本年度は、主に、泥炭採掘に伴う撹乱を受けた北海道北部のサロベツ湿原および定期的な火入れによる撹乱を受けた青森県仏沼湿原におけるシードバンクの構造を、温室における発芽実験をもとに評価した。 1) サロベツ湿原泥炭採掘跡地におけるシードバンク発達様式 【実験方法】 2006年秋(昨年度)と2007年初夏(本年度)に、地上部植被率の異なる4サイトから計400個の100 cc (深さ5 cm)の泥炭を採取した。リターの堆積した2サイトからは、さらにリターを計200個サンプリングした。 温室において、トレイ(16 cm × 23 cm × 6.5 cm)にバーミキュライトを4 cm程度敷き詰め、その上にサンプルを厚さ0.5 cmで蒔いた。表面乾燥とコンタミネーションを防ぐため、サンプルを設置したテーブル全体を寒冷紗で覆い実験を行った。スプリンクラー散水の他に、必要に応じ潅水を行った。各種の発芽数は定期的に記録した。 【結果】  発芽種数・個体数は、地上部植被率の増加とともに増加した。総植被率0.2%のサイトからは合計4種312個体が発芽したのに対し、総植被率68%のサイトからは12種1920個体が発芽した。シードバンクの種組成は、地上部植生の種組成と類似していた。全サイトにおいて、秋に採取したサンプルから発芽した種子数は、初夏に採取したサンプルの種子数を大きく上回っていた。また、秋に採取したリターサンプルからは泥炭サンプルを上回る発芽種子数を得た。即ち、リターが平均5 cm堆積したサイトでは、リターから1308個体が発芽したのに対し、泥炭から発芽した種子は624個体にすぎなかった。
発芽種数・個体数は、地上部植被率の増加とともに増加した。総植被率0.2%のサイトからは合計4種312個体が発芽したのに対し、総植被率68%のサイトからは12種1920個体が発芽した。シードバンクの種組成は、地上部植生の種組成と類似していた。全サイトにおいて、秋に採取したサンプルから発芽した種子数は、初夏に採取したサンプルの種子数を大きく上回っていた。また、秋に採取したリターサンプルからは泥炭サンプルを上回る発芽種子数を得た。即ち、リターが平均5 cm堆積したサイトでは、リターから1308個体が発芽したのに対し、泥炭から発芽した種子は624個体にすぎなかった。 |
【考察】 泥炭採掘後のシードバンク発達は、地上部植生発達と平行して進行している。永続的に埋土する種子は、比較的少ない。よって、シードバンクは植生遷移系列を規定するよりもむしろ個体群維持に機能していると考えられる。さらに、リターはシードバンク発達に大きく寄与していることが明らかとなった。 2) 仏沼湿原におけるシードバンク発達様式 【実験方法】 野外におけるサンプリングデザインおよび温室における発芽実験方法は、サロベツでの研究と同様である。サンプリングは、火災によりリターが焼失した地点(LL)とそうではない地点(AL)を選び、2007年秋にLLでは表層から深さ0-5 cmの泥炭を、LAでは0-5 cmのリターを含む泥炭と 5-10 cmの泥炭を20サンプルずつ採取した。 【結果】(継続中) a) 発芽種数と個体数 全サンプルから14種3439個体の発芽が確認された。LA0-5 cmのサンプルで、最も種数・個体数が高く、9種1798個体を記録した。LA5-10 cmのサンプルでは発芽種数、個体数とも最も少なく、7種660個体であった。LLでは9種981個体が発芽した。 b) 埋土種子集団の種組成と地上部種組成との関係 埋土種子集団優占種はアオミズ、タネツケバナであり、両種ともAL0-5 cmサンプルで最も発芽固体数が多かった。仏沼湿原の地上部植生で優占するヨシの発芽数は極端に少なかった。さらに、タネツケバナ、ノミノフスマなど地上部植生では出現していない種が埋土種子中に見られた。 【考察】 現存植生に出現しない種が埋土種子中から確認されたが、これは、優占種であるヨシおよびリターによる日陰効果により発芽が抑制された可能性を検証する必要がある。ヨシはサロベツ湿原同様、ヨシ植生内では発芽がほとんど認められなかった。さらに、埋土種子集団組成が、撹乱強度の違いにより異なることから、リターが埋土種子集団組成を規定している可能性が示された。 以上のことから、両調査地のシードバンク構造とリターの関係を、温室における発芽実験を用いることで、撹乱の質が異なっていても、リターの存在がシードバンク発達に大きく関与している共通点が示された。 |
地球環境科学院 統合環境科学部門 温暖化影響評価分野
露崎史朗・江川知花
|
大規模撹乱を受けた生態系では、遷移は撹乱前の自然植生に向かい進行するとは限らず、新たな種の侵入定着により遷移系列が変化することもある。本研究の主眼は、1970年から2003年まで泥炭採掘が行われた北海道北部サロベツ湿原において、採掘前に広く発達していたミズゴケ群集に向かう遷移の可能性を探ることにある。採掘地の代表種であるヨシ、ヌマガヤ、ミカヅキグサの発芽および定着特性は、今後の遷移系列を規定する上で重要な鍵となる。野外では、これら3種の発芽定着サイトは異なり、ミカヅキグサやヨシは被度の低い遷移初期に侵入・定着し、ヌマガヤは被度が高くリターが堆積した遷移後期に定着することが示されている。実生発生数の規定要因を明らかにするには、各環境下での種子数と発芽率の2つを測定せねばならない。そこで、(1)泥炭土壌中に含まれる各種の種子数(埋土種子)、および(2)リターが発芽率に与える影響の定量化を、北海道大学先端科学技術センターガラス温室において発芽実験を用いて行った。 【実験方法】 当年生種子の散布時期を過ぎた2006年10月下旬から11月上旬に、1970(1箇所), 1972(2箇所), 1980(1箇所)年採掘跡地から合計320個の100 cc (深さ5 cm)の泥炭土壌を採取した。同様に、リターも100 ccずつ、計160個のサンプリングを行った。サンプルのうち、半量は無処理で発芽試験を行い、残りはインキュベーター中で冷湿処理(3°C)を1ヶ月施し温室にて発芽試験を行った。  トレイ(16 cm × 23 cm × 6.5 cm)にバーミキュライトを4 cm程度敷き詰め、その上に土壌サンプルを0.5 cmの厚さで蒔き出した。土壌表面の乾燥とコンタミを防ぐため、サンプルを置いたテーブル全体を寒冷紗で覆い実験を行った。適宜潅水し、各種の発芽数の記録を6ヶ月間行った(継続中)。
トレイ(16 cm × 23 cm × 6.5 cm)にバーミキュライトを4 cm程度敷き詰め、その上に土壌サンプルを0.5 cmの厚さで蒔き出した。土壌表面の乾燥とコンタミを防ぐため、サンプルを置いたテーブル全体を寒冷紗で覆い実験を行った。適宜潅水し、各種の発芽数の記録を6ヶ月間行った(継続中)。 |
【結果】 1. 総個体数および種数 これまでに、合計18種330個体の実生が確認された。冷湿処理サンプルと無処理サンプルでは、種数、発芽個体数ともに大きな差は見られなかった。泥炭土壌サンプルで種数、個体数ともに最も多いのは、ヨシ、ヌマガヤ、ミカズキグサが混交する1970年採掘地のもので7種52個体が発芽した。1972年採掘地のヌマガヤ優占地のもので5種26個体、1972年のミカヅキグサ優占地のもので4種44個体、1980年の低植被地のもので3種21個体が発芽した。リターからは土壌サンプルを大きく上回る発芽が見られた。即ち、1970年採掘地から10種113個体、1972年採掘跡地からは7種74個体が発芽した。 2. 埋土種子集団中の優占種  低植被域およびミカヅキグサ優占群集では、土壌中からのミカヅキグサの発芽は顕著であった。ヌマガヤ優占群集および3種混交群集では、ヌマガヤ種子が多く発芽し、さらにモウセンゴケの発芽数も多かった。ヌマガヤ種子は土壌中よりもリター中でより多く発芽した。ヨシは、いずれの群集からのものでも、ほとんど発芽しなかった。
低植被域およびミカヅキグサ優占群集では、土壌中からのミカヅキグサの発芽は顕著であった。ヌマガヤ優占群集および3種混交群集では、ヌマガヤ種子が多く発芽し、さらにモウセンゴケの発芽数も多かった。ヌマガヤ種子は土壌中よりもリター中でより多く発芽した。ヨシは、いずれの群集からのものでも、ほとんど発芽しなかった。【考察】 埋土種子集団の種構成は、地上部植生の種構成とよく対応していた。したがって、埋土種子集団の遷移系列は、地上部植生の発達と平行して行われている。また、ミカヅキグサとヌマガヤは、同種の被度の高い群集でのみ種子密度が高く、種子散布距離が比較的短いと推定された。ヨシは、ヨシ群集内でも発芽がほとんど見られず、発芽が抑制されている、あるいは、種子散布量が相対的に少ない可能性が示された。 各群集の埋土種子構成種は地上部の優占種に限られ、種子密度も小さく、採掘跡地の植生回復に対する埋土種子の寄与率は低く、移入種子の方が重要であることが示唆された。また、リターに多くの種子がトラップされるため、発芽後の成長にはリターの発達が重要であると考えられる。 |
生態環境科学専攻地域生態系学講座 露崎史朗、上坂尚平
渡島駒ヶ岳(標高1140 m)は、1929年に起こった大噴火により植生の大部分が破壊された。現在でも、高標高部は大部分が裸地かコケ・地衣類に覆われている(非パッチと呼ぶ)。一方、木本植物では、カラマツが疎らながらも優占するが、その他にミネヤナギと常緑性低木種であるシラタマノキがパッチを形成し定着している。これまでの研究から、ミネヤナギパッチにはシラタマノキパッチや非パッチ域に比べ多くの植物個体が定着しており、ミネヤナギパッチが他種の侵入定着を促進する効果を持つことが示されている。促進効果の要因の1つに、定着したパッチが種子を捕捉する(種子トラップ効果)ことが、世界各地の砂漠やステップ等で確認されている。そこで、種子トラップ効果の観点から、ミネヤナギパッチ、シラタマノキパッチの機能的相違を明らかにするために、ミネヤナギパッチ、シラタマノキパッチ、非パッチ(対照区)間の地表面に存在する発芽可能種子量の違いを把握するために、各地表面から土壌サンプルを採取し、先端科学技術センター温室を利用して発芽実験を行った。 [実験方法]
[実験方法]2001年10月に渡島駒ヶ岳南側斜面、標高約750-880 m地点で、3ハビタット(ミネヤナギ)、シラタマノキ、非パッチ)から20箇所づつを選び、100cm3の採土缶を用い土壌サンプリングを行った。それぞれの箇所について、5サンプルづつを採取し、各ハビタットで計100サンプルを得た。採取したサンプルのうち、半数は、無処理で発芽試験を行い、残りの半分は、5°Cの低温処理を1ヶ月間行った後に発芽試験を行った。 |
各サンプルを、幅10 cm、長さ15 cm、深さ5 cmのポット中にバーイキュライトを敷き、その上に0.5 cm程度の厚さで土壌を置いた。これらのポットを温室内に置いて、発芽が概ね完了する(5ヶ月間)まで発芽試験を行った。出現した実生は針金ピンを実生の側に刺し識別し、種の同定を行った。出現数の多さのためマーキングが困難であったシラタマノキについて始めの10個体を残し除去た以外は、全て個体数を記録した後に取り除いた。
[結果] 土壌100cm3当たりは平均19実生、合計17種の種子植物の発芽が確認された。ハビタット別で見てみると、ミネヤナギパッチで6実生/100 cm3、シラタマノキパッチで48実生/100 cm3、裸地で2実生/100 cm3が確認された。このうち、シラタマノキパッチ中の実生の多くは、シラタマノキ自身であり、またミネヤナギの実生はいずれのハビタットでも全く認められなかった。そこで、シラタマノキ実生数を除いて見ると、ミネヤナギパッチで6実生/100 cm3、シラタマノキパッチで3実生/100 cm3、裸地で2実生/100 cm3となり、ミネヤナギパッチで一番実生密度は高かった。特に、ミネヤナギパッチ中では、イネ科植物(イワノガリヤスとヌカボspp.)の実生が優占した。また、低湿処理区と非処理区間で、ほとんどの種で発芽密度に顕著な差は見られなかった。 [考察] 実生密度から、ミネヤナギパッチは高い種子トラップ効果を持つことが示唆された。これは、ミネヤナギパッチが地表面を風により移動する種子をトラップしやすい構造をしていることと関連すると思われる。シラタマノキパッチは、ミネヤナギパッチより丈が低く、パッチ内照度はミネヤナギパッチより概して低い。種子トラップ効果が低いのは、パッチの構造的な問題と、常緑性等によりパッチ内への種子の侵入(およびあるいは発芽)が妨げられているためと推察される。結論として、ミネヤナギパッチの持つ他種の侵入・定着促進効果の一つとして種子トラップ効果を示すことができた。 |
実験代表者: 露崎史朗(大学院地球環境科学研究科生態環境科学専攻地域生態系学講座)
実験者: 後藤真咲(大学院地球環境科学研究科生態環境科学専攻地域生態系学講座)
有珠山は1977-78年にかけて噴火し、山頂付近の植生は完全に破壊され、当時の表土は厚い火山噴出物に覆われた。その後有珠山火口原では、侵食などにより露出した旧表土から埋土種子由来植物の出現が確認され、噴火から10年後(1987年)には、旧表土中に1 m²当たり約2000種子(25種)が生存していることが分かっている。旧表土中埋土種子集団の、噴火から20年後(1998年)における生存状況を明らかにする目的で行った。埋土種子集団推定は発芽試験法(GM)と比重選別法(FM)の2法を用いて行った。得られた埋土種子集団について種数、密度、および分布を測定し、それらをもとに埋土種子集団の生存様式について考察した。さらに、両埋土種子埋土種子検出方法の結果を比較し、埋土期間の長い種子の検出方法について検討した。 1998年6月、有珠山火口原の4地点(Sites 1-4)において50 cm × 50 cm (Site 2、Site 3は40 cm × 40 cm)の方形区を設置し、火山灰下より旧表土を採取した。方形区を縦横10 cm毎に区切り、100 ml採土缶により各10 cm × 10 cm枠内から2サンプルずつ採取し、一方を発芽試験法に、もう一方を比重選別法に用いた。これを上層(0-5 cm)、下層(5-10 cm)について行い、1方法につき上下それぞれ25(Site 2、Site 3は16)サンプルを得た。
1998年6月、有珠山火口原の4地点(Sites 1-4)において50 cm × 50 cm (Site 2、Site 3は40 cm × 40 cm)の方形区を設置し、火山灰下より旧表土を採取した。方形区を縦横10 cm毎に区切り、100 ml採土缶により各10 cm × 10 cm枠内から2サンプルずつ採取し、一方を発芽試験法に、もう一方を比重選別法に用いた。これを上層(0-5 cm)、下層(5-10 cm)について行い、1方法につき上下それぞれ25(Site 2、Site 3は16)サンプルを得た。発芽試験法: 採取土壌をバーミキュライトを敷いたポット上に1-1.5 cmの厚さで撒き、実験生物センター温室で5ヶ月間発芽試験を行った。出現した実生の同定を行い、数を記録した。記録が終わった実生は取り除き、未同定の場合は別のポットで栽培し、成長後に同定した。 |
比重選別法: 採取土壌にK2CO3水溶液(比重1.54)を加えて遠心し、上澄みを濾しとることにより土壌から種子を分離した(Tsuyuzaki 1994)。実体顕微鏡下で種子を数え、形態から種の同定を行った。同定できないものは実験生物センター温室にて発芽・成長させ同定した。種子の生死判定は押しつぶし法により行った。 GMで合計23種、1 m²当たり1317種子、FMで合計30種、1 m²当たり2986種子の生存が確認された。埋土種子相はエゾノギシギシが優占しており、多年草の占める割合が大きかった。牧草や耕地雑草など比較的攪乱の大きい場所を好む種が半分近くを占めたが、林床に生育するカラフトダイコンソウやイワアカバナ、湿地性であるイグサやハイキンポウゲなどもみられた。木本はカンバの仲間が1種見つかった。種子は上層に多く分布しており、水平方向のばらつきが大きかった。種数、密度、種組成はSiteにより大きく異なった。 10年前と比較すると、FMで種数、密度ともに10年前を上回り、この10年間に顕著な埋土種子の死亡は起こらなかったと考えられた。有珠山火口原において、旧植生に由来する種子が少なくとも20年間は比較的高い密度で生存しており、機会があれば植物供給源として機能する可能性があることが示唆された。 GMとFMの結果を比較すると、単位面積あたりの種数、種子数ともにFMの方が有意に高かった。共通に検出された種は11種で、2方法間で種組成が大きく異なった。共通種の多くは、FMの方が種子検出力は高かったが、種によってはGMの方で多く種子が検出された。これらの結果から、GMとFMはそれぞれに長所短所があり、ひとつの埋土種子集団について異なる推定結果を得る可能性が高いといえた。種子が検出できない理由として、GMでは種子が休眠のため発芽しないこと、FMでは抽出過程で紛失したり形態からの同定が難しいことがあげられた。埋土期間の長い種子は、休眠性が強く、構造が老化しているものが多いため、これらの点を十分に考慮し、複数の検出方法を用いるのが望ましい。 |
申請書課題: 海岸林林床草本群集の多様性維持機構利用室名: 植物ガラス室 (新規) 利用期間: 9年5月1日から10年3月31日まで 実験計画 (目的): 海岸砂丘から海岸林内にかけての草本植物群集の帯状構造について、群集維持のメカニズムを植物の種子散布、埋土種子、実生の定着を調べることにより明らかにする。 (方法): 海岸砂丘域の各植生から土壌と共に土壌中の種子を採集して持ち帰り、温室でポットに蒔き発芽させて同定し、構成種を調べる。実生の同定ができなかったものについては、種の同定ができるようになるまで育てる(必要ならば他のポットに移す)。 (データのまとめ): 各植生帯での埋土種子の構成種の比較、埋土種子構成種と実際の植生との比較、各植生帯間での種子の発芽特性の比較など 使用生物名: 土壌と土壌中の種子。種子から発芽した植物 個体数: 土壌200 mlを240コ (60コ × 4回) 搬入機器: ポット(径10 cm程度)を240コ 利用機器: ポットをのせるトレー 報告書実験代表者 露崎史朗(大学院地球環境科学研究科生態環境科学専攻地域生態系学講座)実験者 小林千穂(大学院地球環境科学研究科生態環境科学専攻地域生態系学講座) 研究成果  海岸砂丘から林内にかけた草本植物群集帯状構造の成立には埋土種子集団の構造が大きく関与していると仮説を立て、その群集維持メカニズムを植物の種子散布、埋生種子、実生の定着を調べることにより明らかにすることを目的として調査を行った。実験生物センター温室においては、埋土種子集団の発芽実験を以下のように行った。海岸砂丘域の各植生帯から土壌と共に土壌中の種子を採集して持ち帰り、温室でポットに蒔き発芽させて同定し構成種を調べた。埋土種子集団は、春(5月22日)および秋(11月4日)の2度、20個の100 cc(深さ5 cm)の土壌を各植生から採取した。観察は、3-7日おきに最低2ヶ月行った。実生の同定ができなかったものについては、種の同定ができるようになるまで大型のポットに移し生育させた。
海岸砂丘から林内にかけた草本植物群集帯状構造の成立には埋土種子集団の構造が大きく関与していると仮説を立て、その群集維持メカニズムを植物の種子散布、埋生種子、実生の定着を調べることにより明らかにすることを目的として調査を行った。実験生物センター温室においては、埋土種子集団の発芽実験を以下のように行った。海岸砂丘域の各植生帯から土壌と共に土壌中の種子を採集して持ち帰り、温室でポットに蒔き発芽させて同定し構成種を調べた。埋土種子集団は、春(5月22日)および秋(11月4日)の2度、20個の100 cc(深さ5 cm)の土壌を各植生から採取した。観察は、3-7日おきに最低2ヶ月行った。実生の同定ができなかったものについては、種の同定ができるようになるまで大型のポットに移し生育させた。 |
得られた結果は以下の通り。
|